真岡市久保講堂について
真岡市久保講堂(旧真岡尋常高等小学校講堂)と久保氏
昭和12年(1937年)、市内在住美術評論家の久保貞次郎(くぼさだじろう)氏(1909~1996年)から「祖父(久保六平氏)の傘寿のお祝いに」と、真岡小学校へ講堂新築の申し出があり、翌13年に竣工しました。その事業費は4万8千円(昭和12年当時の公務員の初任給は75円)で、現在の金額で億の単位に相当し、全額久保家から寄贈されました。当時の真岡町議会では、久保六平氏(1857~1937年)の胸像を建設して感謝の意を表す計画でしたが、久保氏が強く辞退したため、講堂の名称を「久保講堂」と名付けることで了承を得ました。
久保貞次郎氏は、「久保講堂」竣工記念事業として「児童画公開審査会」を開催し、「久保賞」を創設するなど、久保講堂を拠点とした芸術活動を展開しました。
建設当時、真岡市は元より芳賀郡内に千人規模で収容可能な建物がなかったため、真岡小学校児童の体育活動、芳賀地方の児童生徒の作品展示会、戦没者慰霊祭、合併後の市議会など、さまざまな活動の拠点として広く利用され、愛されていました。
久保氏の功績は、講堂とともに半世紀たった現在でも、市民のなかで生き続けています。
久保講堂(旧真岡尋常高等小学校講堂)の移築・保存
その後、真岡小学校の体育館完成や久保講堂の老朽化などの理由により、講堂取り壊しの方針が打ち出されました。しかし、昭和54年(1979年)、同校卒業生を中心とした「久保講堂をのこす会」が署名活動を展開し、市民が一体となり存続活動が繰り広げられました。昭和56年(1981年)、設計者遠藤新(えんどうあらた)博士(1889~1951年)の子息で建築家の遠藤楽(えんどうらく)氏(1927~2003年)をはじめ、専門家による実地調査を行い、「久保講堂は大変な宝物、移築にいくらかかっても残して活用すべき」との提言がなされました。
その結果、昭和61年1月から8月にかけて、約1億円の費用で真岡小学校構内から現在の場所に移築されました。
現在、年間を通して文化祭・芸術祭のギャラリー展をはじめ、児童生徒の書道展、一般市民の各種展示会などが開催され、真岡市の芸術・文化の殿堂として、広く市民に親しまれています。
平成9年5月、県内の建造物としては初となる「国の登録有形文化財」に登録されました。


この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会 文化課 文化財係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎4階
電話番号:0285-83-7735
ファックス番号:0285-83-4070
お問い合わせはこちら









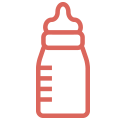
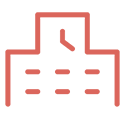
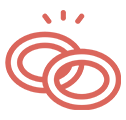

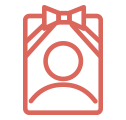
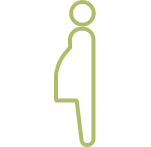



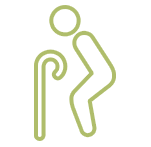







更新日:2024年01月30日