鬼怒水辺観察緑地情報

オオバンの池は今、ガマの穂から綿毛(タネ)が風に吹かれて飛んでいます。一説によると一つの花穂には35万のタネがあるそうです。驚きですね!そのうち発芽できるのはどれほどなのか知りたいです。写真のとおり、水は引いてしまいました。池が干されると、浄化され、水草の多様化が進むように思います。今まで見かけなかった植物が発芽したりすると、楽しくなりますね。春が待ち遠しいです。また、野鳥観察については、雨が降ると水たまりができて、シギの仲間やチドリの仲間などがミミズや昆虫などを食べに集まりますので、そっと双眼鏡でのぞいてみましょう。意外な珍鳥が混じってるかもしれませんぞ!!(12月12日)

センター前の向かって左側に、池の水位調整用湿地帯があります。ここは、春から秋にかけ、ヨシが茂り小動物などの隠れ家、または、トンボやメダカ等、観察スポットになっています。毎年、ヨシ刈りをしてヨシの更新や湿地の環境循環を促し、翌春を待ちます。(12月5日)

タカ科トビですが、ここ鬼怒水辺観察緑地では身近に感じるタカです。鳴き声は「ピーヒョロロ」と鳴きます。サイズもタカの仲間では大きいほうで迫力があります。食性は幅広く魚類やヘビ、カエル、ネズミなどを食べますが、死骸などもたべちゃう。識別は、全体的に茶色で尾羽がバチ型が特徴です。他にもタカの仲間が観察できますので、ぜひお越しください。

春季に引き続き、秋季10月15日、10月22日に真岡市老人研修センター主催の高齢者研修見学会をここ鬼怒水辺観察センターで実施しました。(11月7日)

鬼怒水辺観察緑地内オオバンの池で、双眼鏡やフィールドスコープを使用して野鳥を観察しました。

この時期は、カモ類やサギの仲間などが観察できました。

「この池に来たのは今日が初めて」という方もいて、利用していただけて本当に良かったと思います。また、来てくださいね!

オオバンの池中央部の様子。水深が下がってきていますが、まだカモ類やサギなどが観察できますよ!(11月3日)

オオバンの池北側の様子。水かさが浅くなってきています。オオタカやノスリの狩りの様子が見られるかもしれません。(11月1日)

今回は、鬼怒水辺観察緑地内「オオバンの池」を紹介します。オオバンの池は昭和30年代中頃から50年代前半にかけて砂利採取場でした。その後、採取跡地に水がたまり湿地帯となりオオバンが飛来、そして繁殖地として選ばれたと思います。オオバンは珍しい鳥ではありませんが、繁殖地としては、県内では数少ない貴重な場所となっております。現在では、繁殖数は減少傾向にありますが、この大切な水辺環境を、他の生き物も含め後世に残し伝えられたらと思っています。
「オオバンの池」は、12月から翌年4月まで池の水がなくなります。5月になると水が入り11月頃まで水がありますので、この池でオオバンを見たい方は、池の水があるうちにぜひお越しください。ただし、自然界なので、見れない場合もありますのでご了承ください。

赤トンボといえば、このアキアカネ。この時期、空いっぱいに見られた群生が以前は見られましたが現在では、その景色を見るのは珍しいこととなりました。原因は、気候変動や水田の乾田化、農薬など様々な原因があると思われます。自然と共生する持続可能な農業に期待したいと思います。(10月21日)

10月5日(日曜日)水生昆虫の観察会を実施しました。参加者20名以上の参加があり、わくわくしながら、とても楽しく過ごすことができました。(10月9日)

持ち物はたも網とバケツ、長靴もしっかり履いて池に向かいます。

たも網の使い方や捕まえるコツなどを、講師の新井さんに教わりました。

「とれた!」子供たちは大喜びです。良い体験ができました。

つかまえた水生昆虫を調べてみよう。「なんだろう?」教えて!

場所をセンターに移して、ここで見られる水生昆虫の解説を聞きました。

最後に、今日は取れなかったけど、子供たちは展示したタガメやミズカマキリに手でふれあうことができました。参加された皆さん、本日はご利用ありがとうございました。また鬼怒水辺観察センターに来てくださいね‼また、ボランティア講師の新井さん、大変おせわになりました。

ここ鬼怒水辺観察緑地では、マダラヤンマ(真岡市指定天然記念物)が9月∼10月頃に見ることができるかも⁉国、県ともに準絶滅危惧種に指定されている希少なヤンマです。ブルーの発色がとても綺麗でカメラマンにも大人気。「見たい」と思った方、ぜひお越しください。ただし、採集は禁止してますので、ルールは守ってくださいね!(9月25日)

ギンヤンマの交尾ですね!連結産卵をするそうです。大きさは、約7センチで胸に黒い模様がありません。トンボの池で観察できますが、飛ぶスピードが速いのでホバリングを待つのもよし!(9月16日)

ミズカマキリやコシマゲンゴロウがいた!

アメリカザリガニは水路で4匹捕まえたよ。
9月6日(土曜日)「水辺の生き物をすくってみよう in 鬼怒水辺観察センター」の行事を実施しました。池や水路にはどんな生き物がいるのか、自分で網で捕まえて調べました。参加者は22名。
水辺で遊ぶ機会が少なくなっている今、大人も子どもも身近な水辺の生き物を知るきっかけになればいいなと思います。(9月16日)

「クビアカツヤカミキリ」みなさんご存じですか。全体が黒く胸部(クビ)が赤い3~4センチ位のカミキリです。サクラやウメ、モモなどに被害をもたらす特定外来種です。栃木県内でも近年、分布域を広げつつあります。ここ鬼怒水辺観察センター付近にもサクラがありますが被害木はありませんでした。9月に入ると一足早く落葉が始まるサクラ、末永く「きれいな花を見せてくれ」と、願っています。(8月29日)

8月3日、鬼怒水辺観察センターで夏休みイベントの虫や野鳥の観察会を実施しました。参加者44名、講師6名、スタッフ3名の総勢53名。にぎやかな観察会となり、参加者も大変満足していただけたと思います。

まずは、ボランティア講師さんの紹介からスタート!

出発前に野鳥観察班と昆虫観察班の2班に分かれました。

こちらは、オオバンの池で野鳥観察。双眼鏡の使い方を学びました!

フィールドスコープをのぞくと「いたいたカイツブリの親子だ」

こちらは、昆虫班。トンボやセミ、バッタなどが見られます。でも本命は、ノコギリクワガタ!

当日は、気温も高くセンターで水分補給、そして休憩もしっかり。昆虫の話に興味津々の様子。

本日は、真岡の自然を守る会、真岡自然観察会の協力のもと、立派な観察会を開催することができました。参加していただいた参加者の皆さん及びスタッフの皆様、誠にありがとうございました。

「コウホネとクヌギの木」きれいな風景です。今、トンボの池ではコウホネが黄色い花を咲かせています。また、写真の背景に並ぶ木々はクヌギの木、樹液などに集まる虫たちが観察できます。五感で自然を感じながら、のんびり池の周りを歩くのもよろしいかと思います。

7月23日水曜日鬼怒水辺観察センターで、8月3日、17日に実施予定の夏休みイベントの打合せ会を実施しました。野鳥や昆虫の専門家であるボランティア講師さんたちの多々の意見、誠にありがとうございました。(7月27日)

ハネがとても黒いのが特徴のハグロトンボ。川や池の近くでこの時期見かけるトンボです。飛び方は蝶のようにひらひらととび、涼しさを感じます。神トンボと呼ばれたりしますが、霊が宿るともいわれています。「カッコイイ」と言われるヤンマとは異なるトンボですが、私は、風情があり好きなトンボです。みなさんは、どのように感じますか?(7月16日)

鬼怒水辺観察緑地周辺で、国土交通省による草刈り作業を行いました。センター周辺はすっきりきれいになっています。また、トンボの池の草地では草刈り後、スイバやギシギシ等の植物が新芽を展開しています。ここでよく見られるベニシジミの舞がみられることでしょう。

鬼怒水辺観察緑地内オオバンの池では、カイツブリの親子が見られます。もう親離れの時期ですね。3月に池の浚渫工事をしたのでガマやヨシの景観もきれいですので、出かけてみてはいかがでしょうか。(7月8日)

トンボの池南側散策路の補修工事中の1枚です。今後は、歩きやすくなりますね。(5月28日)

令和7年4月30日と5月7日に、ここ鬼怒水辺観察センターに高齢者研修(真岡4班、真岡2班)として来館利用がありました。まずは施設案内から始めます!

野外に出る前に、オオバンの池でみられる水鳥のカイツブリ等、学習していただきました。

それでは、出発しましょう。いざオオバンの池へ!!

オオバンの池に到着。耳を澄ますとカイツブリの声やオオヨシキリの声なども聞こえてきました。みなさんとても元気です。(私より元気なのは間違いない。)

スコープを利用して観察開始。カイツブリは、巣作り後、産卵、そして6月には子育てを始めます。背中に雛をのせて移動する姿はとても可愛いですよ!

本日の研修予定が終了しました。みなさんお疲れさまでした。

今日は、有意義にお過ごしされたでしょうか?またのお越しをお待ちしております。
(5月17日)

鬼怒水辺観察緑地内で見かける、国鳥「キジ」のペアです。「ケッケーン、ケッケーン」という鳴き声が聞こえたら探してみてください。これからの季節は繁殖期になりますので、あまり近づかずそっと遠くから観察してくださいね!(4月10日)

春に向け、オオバンの池の観察台にある生垣を剪定しました。毎年、田植えが近づく4月下旬頃に、オオバンの池に水が溜まり、待っていたかのように野鳥たちが集まってきます。水辺の野鳥から見た生垣は、目隠しとなりますが、観察者からみた生垣は、低いほうが見やすいですよね。両者のちょうどいい高さとなっていますので、ぜひ、のぞいてみてください。(1月30日)

冬のオオバンの池は、渇水期となり、写真のように4月中旬くらいまで池の水が無い状態になります。雨や雪が降ると凹んだところに水たまりができ、タシギやタケリなどの野鳥が、ミミズや虫などを食べてる様子が観察できますよ。池の水がない今なら、この時期しか体験できない池底散策ができますので、興味のある方は長靴持参で池底を歩いてみてはいかがでしょうか?(1月5日)

この時期、観察センター前の水路でカワセミを見ることができます。写真はオス個体でメスは下クチバシがオレンジ色になります。「翡翠・ヒスイ」と言われるほど美しい色をした鳥です。キレイですよ!!大きさは、17センチ位でスズメより少し大きいです。鳴き声は「ピィー」と高い声を出します。餌の取り方は有名で、水中ダイビングをして小魚を捕まえますが、カエルやザリガニなども食べますね。ぜひ、捕食シーンを見たい方は上着持参で来てみてはいかがでしょうか?(笑)お待ちしてます!!(12月20日)

年の瀬、朝夕の冷え込みが厳しくなってきました。カモたちは換羽が終了すると恋する季節となり、婚活が始まりますね。
写真は、ヒドリガモです。昼間はのんびり過ごし、夕方から活動する夜行性のカモで、水草や植物の種などを食べます。当観察緑地には、カルガモ、コガモなどのほかたくさんの鳥たちが観察できますので、興味のある方は、足を運んでみてはいかがでしょうか。(12月10日)

珍しいガの紹介です。オオバンの池のシンジュの木(ニガキ科)で今年見つかった、シンジュキノカワガの成虫とそのサナギです。とても綺麗なガで、遇産種(自然現象で時々日本にやって来る種)と言われています。調べてみると中国等に生息しているガでニガキ科の樹木の葉を幼虫が食べるようです。西日本では、目撃情報はありましたが、ここでは初めてなので驚きました。本種は、日本では越冬できないと言われていましたので、オオバンの池付近で越冬ができるのか疑問は残りますが、これも暖冬の影響なのか、来年の発生を待ちましょう。(11月6日)

鬼怒水辺観察センターでは、生き物展示として鬼怒川中流域に生息している魚類を4つの水槽に分けて展示しています。今回は一番大きい水槽(幅1200センチメートル)で飼育している日本ウナギを紹介します。愛称は「ウナちゃん」といいます。このウナちゃん、ここに来て2年がたちますが、夜行性なのかずっと昼間は竹筒の中に隠れています。この写真は日中なのに偶然撮れた写真で、砂の中に潜り込む瞬間です。「頭隠して尻隠さず」(笑)。皆さん、ウナちゃんに会いに来てね。

下の写真の食痕を残したと思われる別のオオタカの写真(参考)です。今期は、写真が撮れていなくてすみません。体長50センチメートルくらいで、決して大きいわけではないのにオオタカ?と、思われがちですが、成鳥になると背中が青灰色に変化し蒼鷹(あおたか)と言われていたので、それが由来とか。

センター東口付近の写真です。写真下の芝の所に鳥の羽が映っていますが、鷹などが獲物を狩り、食事をした後の食痕です。羽を見ると、キジバトが食べられてしまったようです。ここ数日前からオオタカの幼鳥?若鳥?が2羽(今季生まれの兄弟?)を、見かけることがありましたので、多分オオタカの食痕かもしれません。でもこんな場所で食べるとはめずらしいですよね。(11月16日)

現在、オオバンの池では数種類のカモたちが観察できます。写真はハシビロガモのペアで扁平なクチバシが特徴ですね。今はまだ、換羽中で写真のような羽ではありませんが、きれいなカモです。他には、オナガガモ、ヒドリガモ、コガモ、カルガモなど200羽位のカモが見られますので、バードウォッチングや写真を撮りたい方は、ぜひ、お越しください。また、この時期はエクリプス(冬羽・繁殖羽)換羽中のカモが多く混じっていますので、興味のある方は、より楽しく観察できますよ。(11月13日)

2023年1月中国科学院天文台で発見された紫金山・アトラス彗星です。とても綺麗ですね!鬼怒水辺観察センター駐車場で、10月15日18時30分頃撮影した1枚です。センター付近は地上光が少なく障害物もないので、天体観測には適している場所です(初級者向き)。ぜひ、星を見たい方はご家族で観測にきてくださいね。(10月31日)

センター南側オオバンの池へと続く道。冬鳥がそろそろやって来る時期、カメラや双眼鏡を持って鬼怒水辺観察センターへ出かけてみてはいかがでしょうか?冬鳥たちが、皆さんをお待ちしてます。(10月30日)

センター周辺の草刈が終了しました。すっきり奇麗になりました。(10月30日)

アキアカネの交尾。暑さが苦手なアキアカネ、涼しい山地から平地に移動して産卵の時期になりました。やっと秋らしくなってきましたね。これからの季節、オオバンの池やトンボの池では、カモなどの冬鳥が渡って来て、にぎやかになることでしょう。(10月18日)

10月6日(日曜日)「赤トンボをつかまえよう」の行事を実施しました。天気が心配でしたが、雨がやんでよかったです。

さあ、赤トンボに会いに行きましょう。

見つけた!狙いを定めて虫取り網を振り上げて、ああ、逃げられた、残念。

虫取り網の振り方を伝授。コツがあるんですよね。

いろんな種類のトンボやバッタまで取れてお父さんも満足。

さあ、みんなでトンボの種類の説明を聞きましょう。

ナツアカネ、アキアカネ、マユタテアカネ、ノシメトンボ、シオカラトンボ、アオイトトンボと6種類のトンボを捕まえることができました。子供たちは真剣に話を聞いていました。

トンボの体の仕組みや見分け方、特徴などを解説。

終了間際に、雨が降り出したのでセンター内で質問の受け答えをした後に解散となりました。昆虫の中でも人気の高い「トンボ」。環境の変化によって、減少傾向にある昆虫とふれあい、子供たちは何を感じ何を思ってくれたのか。

マイコアカネの交尾、ここ鬼怒水辺観察緑地で観察できるトンボです。林に囲まれた池沼や湿地に生息しているトンボで、ここの環境条件が適しているのでしょう。また、10月6日に赤トンボの観察会を実施予定ですが、このマイコアカネ、見ることができるといいのですが。(10月3日)

今年は、カエルの池のガマ刈りを実施しました。池の周りの下草も刈り取り、光や風通しがよくなり植物や昆虫等を観察しやすい環境となっています。昨年同様、草の伸びが早いような気がしますが、みなさんは、どう感じていますか?(9月26日)

ヤンマの仲間では人気者、ギンヤンマです。飛行速度が速く時速60キロメートルはあろうかと、また、ホバリングなども行うきような羽を備え持ったヤンマです。ほかにも、オニヤンマなども有名ですよね。ギンヤンマは7センチ位のサイズで見つけやすいので、ぜひ、観察したい方はいらしてください。(9月19日)

来園者が安心して水辺観察ができること、そして生物により良い環境を作ることを考え水質の向上に取り組んでいるところです。いきもの好きの方、ぜひ、いらしてください。(9月8日)

鬼怒水辺観察緑地では、毎年この時期に池の水質分析調査をしています。(9月8日)

アオイトトンボです。ここ鬼怒水辺観察緑地では、今の時期、よく見ることができるトンボで、色は金属緑色で美しいんですよね。イトトンボの中では、4センチくらいの大きさなので、見つけることは難しいことではありません。しかし、イトトンボの仲間で3センチに満たない種類、例えばアジアイトトンボなどは、見つけにくいんですよね。(9月6日)

ナツアカネの未熟メスかな?よく見かけるトンボです。「よく見かける」ある意味環境変化にも順応できてる貴重なトンボだと思います。オスは、成熟すると真っ赤に染まりこれぞ赤トンボといえる風貌に変化します。アキアカネに似てますが、胸部の模様が少しだけ違いがあること、サイズがやや小さいことで判別できます。今の時期(8月)ここでは、アキアカネは見かけませんからね。(8月30日)

写真はマイコアカネの未熟メスです。みなさんは、逆立ちしているトンボを見たことはありませんか?太陽光が強く、気温が高い日に見ることがあると思います。このポーズは、太陽の方角に腹部を突き上げて日を遮る、つまり、強光を受ける面積を減らしているといわれています。トンボから学ぶ熱中症警戒情報なのです。みなさん、どうぞお気を付けください。(8月10日)

オオバンの池の観察台で見かけたトンボです。写真はまだ未熟のマイコアカネですが、赤トンボの仲間で成熟するとオスは水色顔になり体は真っ赤に染まりイケメントンボに変身します。他にもアオイトトンボなども見られ、とても良い環境となってますので、トンボ好きはオオバンの池へあつまれ。(7月31日)

耳をすませると、カイツブリの鳴き声が聞こえてきます。ここオオバンの池で6月に実施したカイツブリの観察会の時はまだ抱卵中であったが、その後、生まれた雛が親離れをして元気に動き回っています。天敵が多い自然界、無事に成長してほしい。と、私は願う。(7月30日)

当センターから見たトンボの池の1枚です。写真では見ずらいですが5つの池に分かれ、各々が水路を通じてつながっています。池の周りは草地になっていて、季節ごとのトンボやチョウ、バッタなどを観察できますので、どうぞお越しください。また、団体での利用も可能ですので、ご相談くださいませ。追伸、暑い日が続きますが、当センターは指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)指定となっていますので、お気軽に利用ください。(7月24日)

下の写真に引き続き、コフキトンボのメスです。こちらは、帯型となります。ミヤマアカネに似た褐色のはんもんがありますね。打水産卵時に見る水面がとても美しいと思うは、私だけでしょうか?みなさんはどう思われますか。(7月3日)

コフキトンボです。大きさは4センチくらい、「粉吹き」トンボの意味でついた名前のようです。一見シオカラトンボに似てますが複眼色やサイズの違いがあります。この個体は、メス?いや若オスかも?
メスは、2型あるので現段階ではまだわかりませんので成熟を待ちましょう。オスならもっと粉が吹き複眼が黒くなりますね。(6月30日)

6月16日日曜日「カイツブリの親子を見よう」の行事を実施しました。オオバンの池で営巣しているカイツブリのお話と野鳥観察のルールを聞いた後、現地に向かいました。

トンボやバッタなどに子どもたちはドキドキ、ワクワク。もうすぐオオバンの池です。

到着、オオバンの池の観察ポイントなどの説明を聞きました。

観察スコープの使い方を学んで、カイツブリを探そう。「ちょっとむずかしいかも」?

3か所で営巣している情報あり。「いた!カイツブリだ。」

双眼鏡でお父さんも観察中。

見つけました。抱卵中のカイツブリです。そっと観察しましょうね。

スコープでアップで見たい!

カイツブリの親子をみたかったのですが、今年は少し遅れているようです。抱卵中なのでもう少し時間がかかるようですね。雛が生まれたら皆さんまた来てください。

アオモンイトトンボの交尾。ハート形に見えるときもありますがくずれてしまっています。アジアイトトンボに似ていますが少し大きく8節が青色なので区別がつきます。メスはオスと同色タイプと異色タイプがあり未成熟のオレンジ色はとても美しいです。3センチちょっとのイトトンボですが、よく観察すると色々と気づくことがありますので面白いですよ。アオモンに限らずトンボに興味のある方は見に来てはいかがですか。なお、採集目的はお控えください。(6月15日)

市内小学校にて出前講座を実施。野鳥の写真を見たり鳴き声を聞いたり子供たちは興味津々。今度は鬼怒水辺観察緑地の自然の中で、生き生きとした生きものたちを観察しましょうね。(5月29日)

真岡市で見られるチョウの標本です。「このチョウチョ見たことあるー。」と好評でした。

アオハダトンボのオスです。トンボの池で今年初観察ですが、まだ羽化間もないのでしょう、とてもきれいな色をしています。耳をすませば遠くでカッコウの声が聞こえてきます。いいところです、ぜひお越しください。(5月17日)

この時期、ヨシ原から「ギョギョン」という鳴き声が聞こえてきますが、その正体は写真の通り、”オオヨシキリ”という夏鳥です。オスはメスより早くテリトリーを作ってメスを待ちます。大きさはスズメより少し大きいぐらいで虫が好物な野鳥です。ここ鬼怒水辺観察緑地では、ヨシ原がありますので観察したい方はぜひお越しください。(5月8日)

ホソミイトトンボの交尾。このトンボ、元々はもっと南の方にいたのですが、3年くらい前からここトンボの池付近で見られるようになりました。温暖化の影響なのか生息域が広がっているようです。

サギと言ってもコサギやチュウサギ、大きいものではアオサギなどがいますが、この写真のサギはダイサギです。大きさは全長85センチメートルぐらいで、アオサギよりちょっとだけ小さいですが近くで見ると迫力満点。近づきすぎると逃げちゃいますけどね。ちなみに、サギって飛んでいるときは首をたたんで飛ぶんですよ。豆知識として覚えておけば、他の似ている野鳥と見分けるのに役に立ちますよね。
鬼怒水辺観察センターからのお願い
アメリカザリガニとミシシッピアカミミガメを野外に放さないで!
アメリカザリガニとミシシッピアカミミガメは、平成5年6月より「条件付き特定外来生物」に指定されましたので、野外に放したり逃がしたりすることは法律で禁止され、違反すると罰則・罰金の対象になります。
ペットとして飼育されているアメリカザリガニ・ミシシッピアカミミガメは、これまで通り飼うことができ、申請や許可、届出等の手続きは不要です。寿命を迎えるまで大切に飼育してください。
なお、鬼怒水辺観察センター管理地内の池には絶対に放したり逃がさないでください。また、引き取り等もできませんのでよろしくお願いいたします。
鬼怒水辺観察センター(真岡市防災センター)では、鬼怒水辺観察緑地の自然を 写真などで紹介しています。
- 開館日 :毎週水曜・土曜・日曜日と国民の祝日
- 開館時間:午前9時~午後3時
- 入館料 :無料
- 駐車場 :乗用車45台(無料)









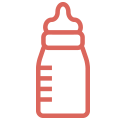
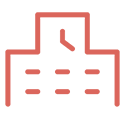
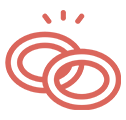

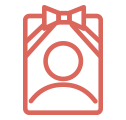
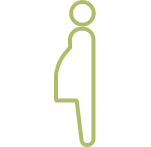



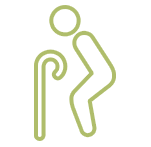







更新日:2025年12月15日