根本山自然観察センター 行事報告
1月17日(土曜日)「ため池のカモを見に行こう」
冬こそ、鳥を見に行こう。今回は、カモを見にため池へ出かけました。冬の自然観察は服装が大切。暖かい上着やズボンはもちろん、帽子と手袋も必要です。厚手のくつ下もはけば、完璧。さあ、出発です。


まずは、双眼鏡やスコープを使ってみましょう。遠くに見える小さいカモも、双眼鏡を使えば大きく見えます。慣れてくると、池のふちの木の枝のかげにコガモが10羽以上見えました。根本山の野鳥クラフトでも人気のあるかわいいカモです。


1時間ほどの観察で、氷の上を歩くカルガモ、ため池の上空高く飛ぶオオタカ、センダンの実を食べるヒヨドリの群れ、ジェージェーと鳴きながら飛んでいくカケスなど、野鳥クラフトで作れる鳥たちを見ることができました。

ため池のカモは、3月ごろまで見られます。見に行く時は、双眼鏡だけではなく、図鑑を持って行くのがおすすめです。新しい出会いがきっとありますよ。冬を楽しんでね。
12月25日(木曜日)、26日(金曜日)、27日(土曜日)、1月6日(火曜日)、7日(水曜日)
「熊手貸します!落ち葉のプールを自分で作って遊んじゃおう」
この冬も、根本山の雑木林は落ち葉がいっぱいです。そこで、熊手を無料で貸し出すので、自分たちで落ち葉のプールを作って遊んでください!という企画を冬休みに実施しました。


空気がピリッと冷たい晴れた日、元気いっぱいの家族連れが参加。家族で作った落ち葉のプールにもぐったり、飛び込んだり、明るい笑い声が聞こえていました。


落ち葉かきは、冬の大事な作業のひとつ。みんなが落ち葉をかいてくれたおかげで、地面に落ちている植物のタネを食べにカワラヒワやルリビタキが来たり、春になればタチツボスミレやフデリンドウが咲き出します。いろいろな生き物が生きている、楽しい場所になるってこと。
それでは皆さん、今年も里山の生き物とともに明るい一年になりますように!
11月29日(土曜日)「オオムラサキの幼虫を探そう」
猛暑だった今年の夏、雑木林の樹液にいたオオムラサキは産卵し、幼虫が生まれ、そろそろ冬越しの季節になりました。幼虫は、どこでどんなふうに冬を越すのか、観察しました。


夏から秋の間、エノキの枝先で葉っぱを食べていた幼虫は、11月中旬から幹を歩いて根元まで下りて落ち葉の下で冬を越します。そこで、昆虫の林、トンボの水辺のエノキを囲んで幼虫を探してみました。ひとりが「いたー!」と声が上がると、次々に見つかります。あれ?よく見ると、みんな同じじゃないね。


根本山にはオオムラサキだけでなく、そっくりなゴマダラチョウ(在来種)の幼虫もいます。「これ、オオムラサキ?ゴマダラ?どっちかな?」写真と見比べながら調べると、オオムラサキが80匹以上、ゴマダラチョウが4匹見つかりました。


林縁や車道沿いの植え込みには、高さが50センチにも満たない小さなエノキが育っています。まだ緑色の葉っぱの上にいた幼虫は、これまたオオムラサキにそっくりなアカボシゴマダラ(外来種)。学校や家の近くでエノキの幼木を見つけたら調べてみよう。アカボシゴマダラがいるかもしれません。


オオムラサキには、広い雑木林と林縁のエノキが必要です。これからもずっとオオムラサキが暮らせるように、若いエノキや樹液の出るコナラやクヌギも育てる必要があります。観察した後、すべての幼虫は根元に戻し、落ち葉をたくさんかけておきました。無事に冬を越せますように、と願いを込めて。
地図を手にクイズを探しに行こう!
クイズを見つけると、解答用紙に答えを記入していきます。各クイズには“ひみつの絵”も描かれていて、それも忘れずに描き写します。近くに腰を下ろし、時間をかけて絵を描く子どもの姿も見られました。


およそ1時間かけて5つのクイズを巡り、自然の中での探検と謎解きを満喫していました。大人から子どもまで、秋の根本山での探検を楽しんでいる様子がとても印象的でした。
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 根本山自然観察センター
〒321-4311
真岡市根本56番地11
電話番号:0285-83-6280
ファックス番号:0285-83-4624









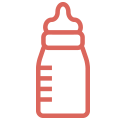
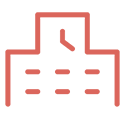
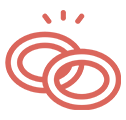

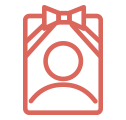
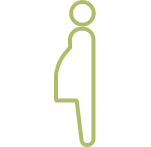



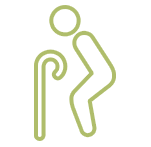







更新日:2026年01月28日