食品ロスを減らそう!
食品ロスとは
食品ロスとは、本来食べられたはずなのに廃棄されてしまった食品のことをいいます。
大切な資源の有効活用や環境負荷への配慮等の観点から、食品ロスを減らすことが必要です。
食品ロスの現状
環境省の「食品ロスの発生量の推計値」によると、令和2年の食品ロスの発生量は522万トンでした。
食品ロスの内訳は、事業系食品ロスが275万トン、家庭系食品ロスが247万トンとなっています。
事業系食品ロス・・・事業活動を伴って発生する食品ロス
家庭系食品ロス・・・各家庭から発生する食品ロス
食品ロスを国民一人当たりに換算すると、お茶碗約1杯分(約113グラム)の食品が毎日廃棄されていることになります。
食品ロスの原因
家庭で発生する食品ロスの原因は、大きく3つに分類されます。
1 食べ残し・・・食べきられずに廃棄されたもの
2 直接廃棄・・・賞味期限切れなどの理由で、手つかずのまま廃棄されてしまうこと
3 過剰除去・・・野菜や果物の皮を厚くむき過ぎるなどして、食べられる部分まで取り除いてしまうこと
食品ロスを減らすために
食品ロスを減らすためには、家庭で食品ロスが出ないようにするだけでなく、食べ物を買うお店、食べるお店でも食品ロスを減らすことを意識することが大切です。
食品ロスを減らすためにできる取り組みを、場面ごとにご紹介します。
飲食店で食事をするとき
注文しすぎない
お店に小盛りやハーフサイズメニューがある場合は、積極的に活用し、食べきれる量を注文しましょう。
とちぎ食べきり15(いちご)運動の実践
会食(飲み会、食事会など)の際には、「いただきます!」のかけ声後と、「ごちそうさま!」のかけ声前のそれぞれ15分は、食べることに集中し、料理の食べ残しがないように心がけましょう。

買い物をするとき
買いすぎを控える
買い物に出かける前に冷蔵庫の中身を確認し、必要なものをメモして買い物に行くことで、買い過ぎを防ぎましょう。
少量パックやばら売りを利用し、必要な分だけ購入するようにしましょう。
陳列された順に買う(手前どり)
すぐに食べる商品は、賞味期限や消費期限の長い商品を選択するのではなく、手前に陳列された商品から購入しましょう。

消費期限と賞味期限の違いとは?
消費期限・・・過ぎたら食べない方がよい期限。
賞味期限・・・おいしく食べることができる期限。この期限を過ぎてもすぐに食べられなくなるわけではない。
調理をするとき
料理を作り過ぎない
食べきれる量の調理を心がけましょう。
食材を上手に使い切る
野菜や果物の皮を厚くむき過ぎないようにしましょう。
食材が余ったときには、インターネットなどで、使いきりレシピを検索してみましょう。
保存をするとき
冷凍などでの保存を検討
食べきれなかった食品については、冷凍などの傷みにくい保存方法を検討しましょう。
保存した食品の把握
保存していた食品を忘れてしまわないように、冷蔵庫の中の配置方法を工夫しましょう。
食品ロス削減に関する栃木県の取り組み
食品ロスに関してもっと詳しく知りたい方へ
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 環境課 ごみ減量係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎2階
電話番号:0285-83-8126
ファックス番号:0285-83-8392
お問い合わせはこちら









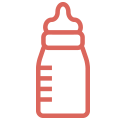
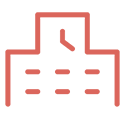
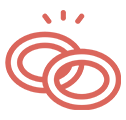

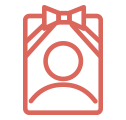
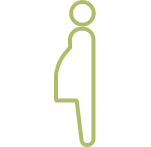



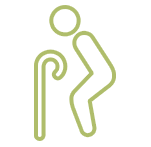







更新日:2023年11月06日