風鈴

目と耳で感じる「涼しさ」。日本の夏の風物詩でもある風鈴は、私たちの心をいやしてくれる存在ですね。自然教育センターでつくることができる「風鈴」は自然の素材を生かしています。
このページでしっかり事前学習をして、実際に世界で一つだけの風鈴を作ってみましょう。
 |
どうやって作るんだぴょん?
|
|
このページをしっかり読めば作ってみたくなるよ!
|
 |
活動のねらい
- 陶の板での風鈴づくりにチャレンジし、音色を楽しむことができる。
- 道具を安全に使うことができ、加工するおもしろさを味わう。
準備する物と活動場所
みんなが準備(じゅんび)するもの
<準備物>
- 軍手
センターにある道具
<道具>
- 台になる木
- のこぎり
- ドリル
- やすり
- はさみ
- ラジオペンチ
- げんのう(金づち)
- カラーペン
<材料>
- 木の枝
- シュロ縄
- たたみ糸
- 陶の板(3枚)
※穴がひとつの板を2枚、穴がふたつの板を1枚 - 釘
- 風を受ける紙
活動場所
- 研修室
活動人数の関係で、ボランティア室になることもあります。
風鈴をつくってみよう
1.幹づくり

まず、風鈴の幹となるパーツを作ります。
たくさんの枝の中から、好みの太さの枝を選び、15cmぐらいになるようノコギリで切ります。
次に、枝の左右の2か所にドリルで穴をあけます。
穴の向きをそろえるようにあけましょう。

切り口はヤスリできれいに整えておきましょう。
2.陶の板

風鈴の下の部分に吊るす「陶の板」を選びます。
- ひとり3枚
- 穴がひとつの板を2枚、穴がふたつの板を1枚選びます。
穴がふたつの板が真ん中になります。
ペンで好きなように色を染めたり、すてきな絵を描いたりしてみましょう。
3.釘打ち

幹の3か所に「釘」を打ちます。
中央に1本、ちょうど同じくらいの場所になるよう左右に1本ずつ打ちます。
「ラジオペンチ」を使って、釘をおさえ、最後まで打ち込まないようにしましょう。
ふたりで協力するとよいですね。
4.糸通し

打った釘に「たたみ糸」をひっかけます。
陶の板の穴にたたみ糸を通し、3枚の板の高さが同じくらいになるよう長さを調整します。
たたみ糸が輪になるようにして結びます。
結び目はちょうど釘の位置に動かすと目立たなくてよいですね。
高さが決まったら、釘を最後まで打ち込みましょう。
余分な糸ははさみで切ります。
真ん中の板の下の穴に、「風を受ける板」を結びます。
5.シュロ縄

幹の左右にあけた穴に、「シュロ縄」を通します。
長さを調整し、止め結び(だんご結び)をします。

止め結び
6.完成

完成です。
風を送り、音を楽しんでみましょう。
後片付け
次の活動のために、きちんと後片付けをしましょう。
- 道具は元の場所やケース内に戻す。
- 切った糸や削りカスを集めてゴミ箱に捨てる。
- ほうきやちりとりで部屋を掃除する。
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会 自然教育センター
〒321-4365
真岡市柳林1140番地2
電話番号:0285-83-1277
ファックス番号:0285-83-1278
お問い合わせはこちら









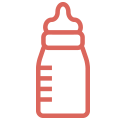
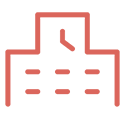
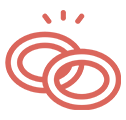

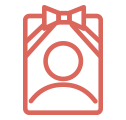
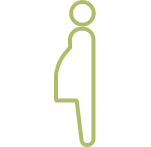



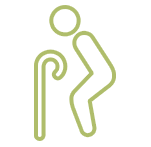







更新日:2025年01月08日