勾玉

自然教育センターでは、創作活動のひとつに「勾玉」を作ることができます。古代の日本人の装飾具のひとつで、魔よけ・厄除け・権力の象徴など、様々な目的があるそうです。勾玉作りを通して、古代の人々の生活を想像してみませんか?
このページでしっかり事前学習をして、実際に作ってみましょう。
 |
昔の人はすごいなぴょん!
|
|
このページをしっかり読めば作ってみたくなるよ!
|
 |
活動のねらい
- 古代の人々の生活の様子を想像しながら、勾玉作りの体験をすることで、我が国の歴史に愛着をもつことができる。
- 道具を安全に使うことで、古代の人々の技術の高さを実感することができる。
準備する物と活動場所
みんなが準備(じゅんび)するもの
<準備物>
- 軍手
- 長ズボン(季節によってはハーフパンツも可)
- 水筒
- マスク(必要な人)
センターにある道具
<道具>
- ろう石
- 鉛筆
- きり
- 棒ヤスリ
- 平ヤスリ
- 紙ヤスリ
- ひも
- 雑巾
- 新聞紙
- トレイ
- 油性ペン
- 新聞紙
活動場所
活動場所
- 作業用テント

勾玉を作ろう
1.形を描く

ろう石に、勾玉の形を「鉛筆」で下書きをします。
ろう石いっぱいになるくらい大きく描きましょう!
小さく描くと削る部分が多くなります。

先に、ひもを通す穴を「きり」で開けます。
下に雑巾を敷くと動かずに安定します。
2.削る・磨く

まずは、余計な部分を「平ヤスリ」で削り落としていきます。
たくさん粉が出るので、周りにまき散らさないように気を付けましょう。
へこんでいる部分は「棒ヤスリ」で削っていきます。

まだまだ角ばっているので、丸く磨いていきます。
対称にするために、側面の中心に「鉛筆」で線を描きます。その線を消さないように、角を落としていきます。
「平ヤスリ」で、だいたいの形を整え、「紙ヤスリ」で磨きます。

へこんでいる部分は「棒ヤスリ」を使って、整えていきましょう。

3.色を付ける

「油性ペン」で色を着けてみてもよいですね。もちろん、素材そのものの色を楽しむのもよいと思います。
4.ひもを通して完成

最初に開けた穴にひもを通して完成です。
世界でひとつだけの素敵な勾玉ができましたね。
後片付け
次の活動のために、きちんと後片付けをしましょう。
- たくさんの粉は、集めて地面に落とします。そっと落とさないと、粉が舞って大変ですので、思いやりの行動をお願いします。
- 平ヤスリと棒ヤスリは、ブラシで汚れを落としてから種類別に戻してください。
- 紙ヤスリはそのまま処分します。
- きりはキャップをして元に戻しましょう。
- トレイも粉を落として戻してください。
- 最後に使ったテーブルや椅子の粉を、水洗いします。ジョーロで水をかけ、ワイパーで水と汚れを落としましょう。
衣服にも白い粉がたくさん付いています。そのままセンターの建物内に入れないので、屋外でしっかりと落としてください!
ふりかえり
活動の後はしっかりふり返りをします。
- どんな学びがありましたか。また、これからの生活で、どんな場面で生かせそうですか。具体的に考えてみましょう。
- 素材を加工することで、どんな発見がありましたか。
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会 自然教育センター
〒321-4365
真岡市柳林1140番地2
電話番号:0285-83-1277
ファックス番号:0285-83-1278
お問い合わせはこちら









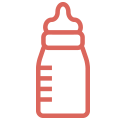
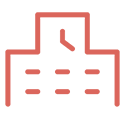
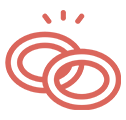

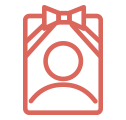
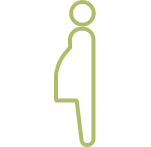



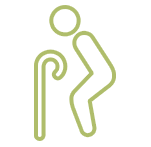







更新日:2025年09月16日