野外炊さん

火をおこして、外で調理する「野外炊さん」の紹介ページです。どうして外で食べる料理はおいしいのでしょうか。その秘密は、「協力」にあるのかもしれません。
このページでしっかり事前学習をして、実際に自然教育センターで作ってみましょう!
 |
野外炊さんはどういう流れで活動するんだぴょん?
|
|
安全に活動するため、 このページをよく確認しよう!
|
 |
準備する物と活動場所
みんなが準備(じゅんび)するもの
- 調理ができる服装
- 軍手
- 長ズボン
※熱中症対策で、かまどの近く以外はハーフパンツ可 - 調理の材料
入所時などに、最寄りのスーパーマーケットで買い出しすることもできます。
購入した食材を、栄養指導室の冷蔵庫で保管することもできます。
センターにある道具
野外調理に使う道具は何かをよく考えて、必要な数だけを持っていきましょう。
<栄養指導室にあるもの>
●まぜる 入れる
- ボウル(特大45cm・大35cm・中30cm・小22cm)
- ステンレスざる(中35cm・小30cm)
- 泡立て器
- さいばし
●切る むく あける
- 包丁と包丁用ふきん(青色)・・・グループで2本程度
- まな板
- ピーラー・・・皮をむく時に使う
- オープナー(かん切り・せん抜き)
●よそう もりつける
- しゃもじ
- お玉
- トング
- さいばし
●いためる 焼く
- 竹ターナー・・・炒めるときに使う
- フライ返し(フライパン用)
- 大きいフライ返し(鉄板用)
●はかる
- 計量カップ(200mL)
- 計量スプーン
- 電子はかり
- はかり
●食器(使い捨て)
- 平皿(大・中・小)
- カレー皿
- どんぶり(大・小)
- 木製スプーン
- 木製フォーク
- 割りばし
- 紙コップ
●運ぶ
- 食器かご・・・物品を運ぶときに使う
<外倉庫にある物>
●たく いためる 焼く にる わかす
- 飯ごう(4合用) ※飯ごう用しき板
- なべ と なべぶた ※なべ用しき板
- フライパン(小) ※フライパン用しき板
- フライパン ※フライパン用しき板
- 鉄板(小)
- 鉄板(大)
- 焼きあみ (2枚まで)
- やかん
- 羽釜(3升炊き)
- 中華鍋
- かまど(グループで1個)
●洗う ふきとる
- 外用ふきん(グループで2枚)
- 外用ぞうきん(グループで2枚)
- たわし(グループで2個)
- スポンジ(グループで2個)
- 洗ざい(グループで1個)
- 金だわし(必要があれば貸出可)
<炊事場でわたすもの>
- マッチ(3~6本) →火おこし後、すぐに返す!
- 新聞紙
- たき付け用わりばし
- 火ばさみ
- こげ付き防止のクレンザー
- テーブルクロス(グループで1枚)
- いす用シート(グループで2枚)
活動場所
<天気がよい場合>
- 野外炊事場
自分たちで使うテーブルの場所を決めておきましょう。
<天気が悪い場合>
- 作業用テント
あまり広くないので、人数が多い場合は、思いやりの心をもちましょう。
<荒れた天気の場合>
- 栄養指導室ほか
人数によって場所が変わります。先生の指示をよく聞きましょう。
野外炊さんの流れ(例)
◆活動前
- 準備の役割分担
室内から運ぶ係、外倉庫から運ぶ係、かまど係に分かれる。 - 場所決め
テーブルの場所を決める。足りなかったら、作業用テントから持ってくる。
◆係の仕事の例
<室内から運ぶ係>
- 物品貸出票に書かれた数だけ、調理器具や食器を借りる。
- 野外調理場に運ぶ。
- 調理をする。
- 数を確認して戻す。
<外倉庫から運ぶ係>
- 物品貸出票に書かれた数だけ、調理器具や食器を借りる。
- 野外調理場に運ぶ。
- 水道で、調理器具を水洗いし、外側を外用ふきんでふきとる。
- 調理をする。
- こげつき防止のため、火にかける前に、飯ごうやなべの外側にクレンザーを塗る。
- 数を確認して戻す。
<かまど係>
- かまどと遮熱板を外倉庫から運ぶ。
- 薪ケースに薪を必要量入れる。
- マッチ、新聞紙、たきつけ用わりばし、火ばさみを受け取る。
- 火をおこし、火力の調節をする。(マッチはここで回収)
- 完全に冷えたら、かまどと遮熱板を倉庫に戻す。
- 残った薪は小屋に戻す。(少しでもこげている薪は戻さない)
◆調理方法(ちょうりほうほう)
- 手をよくあらい、ゴム手袋を着ける。
- 食材は水でよくあらう。
- 十分に火を通す。※ヤケドに注意する
- できあがったら早いうちに食べる。
◆あとかたづけ
- 使った調理器具の数を確認する。
- 室内から持ってきたものは、外の水道であらい、最後の仕上げを栄養指導室であらう。
- 外倉庫からのものは、外の水道でしっかりあらう。
- よく水切りして、外用ふきんでふきとる。
- あらい残しがないか、先生とセンターの先生にチェックしてもらう。
- 数を確認して、元の場所にもどす。
◆ゴミの処理(しょり)
- しっかり分別
生ゴミ・燃えるゴミ・ペットボトル・缶・ビンに分別する。
※ペットボトルはラベルをはがしてつぶす。 - 生ゴミ
流しの生ゴミを穴に流さないよう注意する。
残っていると野生動物が来てしまうため、すみずみまで後片付けをする。 - 捨てる場所
多目的ホールの東南にあるゴミステーションにもっていく。
おまけ(飯ごうの炊き方)
 |
飯ごうの炊き方を紹介するね!
|
|
これは勉強になるぴょん。
|
 |

<お米と水の量>
センターの飯ごうは1個で4合まで炊けます。
お米をよくとぎ、飯ごうにいれ、水を入れます。水は1合にあたり約200mLが適量です。飯ごうにも印がついていますので、それを目安にしましょう。
- 2合・・・一番下の印
- 3合・・・印と印の間
- 4合・・・一番上の印
30分ほど水につけこんでおきます。
!やっておこう!
火にかける前に、こげ付き防止のためクレンザーをぬっておきましょう。

<火にかける>
かまどの上にそっとのせます。このとき、取っ手が下にならないように、ふたの上に角材を置き、ストッパーにしておきましょう。
初めは弱火です。
火の大きさは、飯ごうの底に炎の先が当たるくらいがちょうどいいです。
かまどから火がはみ出している場合は、薪を抜くなどして、火加減を調節しましょう。

<火の調整>
火にかけていると。そのうち飯ごうから水が吹きこぼれてきます。
そしたら、強火に切りかえます。かまどから火が飛び出すくらいに強くしてみましょう。
※ヤケドに注意です。
吹きこぼれが収まったら、再び弱火です。
ふたに火ばさみを当てて、グツグツといった手応えがなくなったら、そろそろ炊き上がりです。
※こげた匂いは、炊きすぎのサインです。要注意!
<炊き上がり>
火から下ろし、先生かセンターの先生に中を確認してもらいましょう。
最後に飯ごうをひっくり返して、10分ほど蒸らします。
食べるときに、しゃもじで全体を混ぜると、水分がよく混ざり、よりおいしくなりますよ!
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会 自然教育センター
〒321-4365
真岡市柳林1140番地2
電話番号:0285-83-1277
ファックス番号:0285-83-1278
お問い合わせはこちら









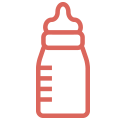
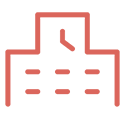
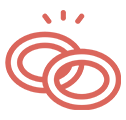

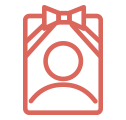
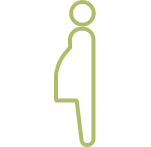



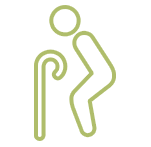







更新日:2024年04月15日