介護保険Q&A(よくあるご質問)
介護保険制度とは何ですか?
介護保険制度は、加齢や病気などにより介護が必要になった高齢者などが、必要な介護サービスを受けられるよう、40歳以上の人が保険料を納めて支え合う仕組みです。
市区町村が運営主体(保険者)となっています。
どのようなサービスが受けられますか?
介護保険では、体の状態や生活に合わせて、次のようなサービスが利用できます。
- 訪問サービス:ヘルパーが自宅に来て、食事や入浴などを手伝ってくれます。
- 通所サービス:デイサービスなどで、食事やリハビリ、交流の場が提供されます。
- 短期入所(ショートステイ):数日間、施設で過ごすことができます。
- 施設入所:長期間暮らせる施設(介護保険施設)に入所し、必要な介護サービスの提供を受けられます。
- 福祉用具・住宅改修:手すりや車いすのレンタルや販売、段差の解消や滑りの防止などの住宅改修工事が支援されます。 など
どのサービスが使えるかは、要介護度や生活の状況などによって決まります。
まずはケアマネジャーや地域包括支援センター、市高齢福祉課にご相談ください。
介護保険のサービスを利用するには、どうすればよいですか?
市町村の介護保険担当窓口に要介護認定の申請を行います。
その後、認定調査と主治医意見書に基づいて介護認定審査会で「要介護度」が審査・判定され、市町村が要介護認定を行います。
認定を受けた方は、ケアマネジャーと相談してケアプランを作成し、サービスの利用が始まります。
なお、要支援認定についても、基本的に要介護認定と同様の手順で審査・判定が行われます。
要介護認定とは何ですか?
要介護認定とは、介護がどの程度必要かを判断するための制度です。
「要支援1・2」「要介護1~5」の区分に分かれており、それぞれの区分に応じてサービスが提供されます。
要介護認定結果に不服がある場合はどうしたらよいですか?
市町が行う要介護認定等の処分に対する不服申立てについては、栃木県が設置する介護保険審査会において、公正な審理裁決を行い、利用者の権利利益を保護するとともに、介護保険制度の適正な運営を確保します。
サービス利用時の自己負担はいくらですか?
原則として、保険対象サービス費用の1割が自己負担になります。
ただし、一定以上の所得がある人は2割または3割が自己負担になります。
残りの費用は保険で給付されます。
なお、サービス計画作成等のケアマネジメントの費用は全部が保険給付されます。
訪問介護やデイサービスの利用回数に制限はありますか?
要介護度に応じて、月ごとの利用限度額が決まっています。
限度額の範囲内であれば、回数や組み合わせは自由です。
ただし、限度額を超えた分は全額自己負担となります。
第2号被保険者(40~64歳)で介護サービスを受けられるのはどのような場合ですか?
老化による病気が原因で介護が必要になった場合に限られています。
老化による病気は、次の16疾病が特定疾患として定められています。
- がん末期
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
介護保険料は誰が払うのですか?
原則、40歳以上の人が納めます。
- 40歳~64歳(第2号被保険者):医療保険と一緒に保険料を納めます。
- 65歳以上(第1号被保険者):市区町村が決めた額を年金から天引き(特別徴収)または納付書などで納めます(普通徴収)。
なぜ介護保険料を納めないといけないのですか?
介護保険は、介護を必要とする方を社会全体で支える目的で作られた制度です。
高齢になって介護が必要になったときに、誰もが安心してサービスを受けられるように、40歳以上の被保険者の方に保険料を納めていただき財源としています。
今は、元気だからといっても、いつ介護が必要な状況になるかわかりません。
もしもの時の備えであり、「お互い様」の制度となっております。
安定的に介護保険の財政運営ができるようご協力をお願いいたします。
保険料を特別徴収(年金から差し引き)から普通徴収(納付書払い又は口座振替)に変更できますか?
年金を年額18万円以上受給している方は、特別徴収の方法によって保険料を納付することと法律で定められています。
納付方法をご自身で選択することはできませんので、ご了承ください。
40歳以上の人は全員介護保険に入りますか(被保険者になりますか)?
原則、65歳以上の方は「第1号被保険者」、40歳以上65歳未満の医療保険加入者は「第2号被保険者」となります。
ただし、40歳以上でも、次の方は介護保険の被保険者にはなりません。
- 40~64歳で、医療保険に加入していない方(生活保護をうけることにより国民健康保険の適用除外になった方など)は対象外となります。
なお、医療保険に加入していない方でも65歳以上になれば被保険者になります。 - 海外に長期滞在しており日本に住民票がない場合は被保険者になりません。
- 次の「適用除外施設」に入所している方は被保険者になりません。
- 指定障害者支援施設(障害者総合支援法)
- 障害者支援施設(身体障害者福祉法)
- 児童福祉法の規定による医療型障害児入所施設
- 内閣総理大臣が指定する医療機関(児童福祉法)
- 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法の規定による施設
- ハンセン病問題の解決の促進に関する法律に規定する国立ハンセン病療養所等
- 生活保護法に規定する救護施設
- 労働者災害補償保険法に規定する労働者災害特別介護施設
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する療養介護を行う病院
要介護認定を受けている人が他市町村に引っ越した(転出した)場合はどうなりますか?
要介護認定または要支援認定を受けている方が他の市町村に転出するときは、認定等に関する情報を記載した受給資格証明書を交付します。
転出先の市町村で14日以内に受給資格証明書を添えて手続きをした場合は、改めて介護認定審査会での審査・判定を経ることなく認定されます。
自分の住所地以外の事業者のサービスを利用できますか?
自分の住所地以外の介護サービス提供事業者を利用したり、施設サービスを利用することもできます(地域密着型サービスを除く)。
事業者のサービスに不満があるときはどうすればよいですか?
サービス提供事業者の苦情受付窓口、担当のケアマネジャー、市の高齢福祉課や地域包括支援センター、国民健康保険団体連合会にご相談ください。
- 高齢福祉課:0285-83-8094
- 地域包括支援センターもおか:83-8132
- 地域包括支援センターにのみや:74-5139
- 国民健康保険団体連合会:028-643-2220
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 高齢福祉課 介護保険係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎1階
電話番号:0285-83-8094
ファックス番号:0285-83-8554
お問い合わせはこちら









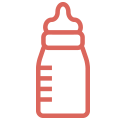
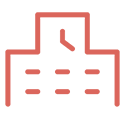
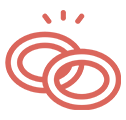

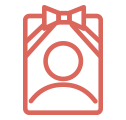
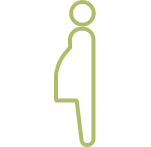



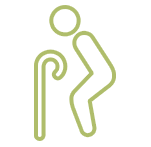







更新日:2024年05月10日