真岡ふるさと遺産認定制度について
初の「真岡ふるさと遺産」認定証交付式を実施
「真岡ふるさと遺産」とは、真岡市の歴史、文化、伝統産業等の文化資源を認定し、これに関わる人々の尽力を顕彰するとともに、真岡市の魅力向上と次世代への継承を図るものです。
初回となる認定は市制施行70周年記念事業の位置づけで、令和7年3月12日付で真岡の夏祭り荒神祭・久下田祇園祭・真岡木綿の3件の遺産で、認定証の交付と記念品の授与を市長公室で行いました。

令和7年3月12日認定証交付式 市長公室にて関係者の皆様と石坂市長、記念品の看板
真岡ふるさと遺産の認定基準について
地域の歴史・文化・自然等に深く関わり、真岡市の特色を象徴するもので、発祥から50年以上の年月が経過しているもの、他5つの認定基準にすべて該当するものについて認定します。
令和6年度、真岡市制施行70周年、二宮誕生70年の記念事業として認定を受けたのは、以下の3件です。
1.真岡の夏まつり荒神祭
「真岡の夏まつり荒神祭」は、日本の夏祭り百選にも選ばれている真岡市最大のイベント。お祭り大好き真岡っ子をはじめ、市内外から、毎年多くの人が訪れます。花火大会における神輿の川渡御、屋台のぶっつけは最大の見どころであり、これらを同時に見られる祭りはほかに類を見ないとされています。
祭りの起源としては、明治期以前から真岡三町である荒町、田町、台町がそれぞれ祇園祭を開催していたことにあるといわれています。
戦後、昭和28年に「真岡三町連合会」が発足し、翌年の昭和29年に市制施行で真岡市が誕生した年に、祭りの主軸となる真組(しんくみ)・真若(しんわか)が結成。この年に初めて三町の祭りと大前神社の祇園祭の一本化を図りました。
その後、市制の発展とともに、「花火大会の開催」「並木町の参加」などを経て、現在に至っています。

華やかな花火と神輿の川渡御

大前神社の宮入り
2.久下田祇園祭
久下田祇園祭の起源は、大正9年に建立された大神輿(おおみこし)が現存しており、令和2年に建立百年の記念式典が行われています。
戦前戦後の混乱を経て、昭和30年以降、旧二宮町の中心の賑わいとして商工会を中心に様々なイベントとともに開催されました。
真岡を代表する夏祭りとして「真岡の五大夏祭り」とされており、久下田のメインストリートが歩行者天国となり、千代ヶ岡八幡宮の大神輿や地域神輿、子ども神輿が練り歩く活気のある祭りです。

久下田祇園祭の宮入

久下田メインストリート
3.真岡木綿
真岡木綿は、江戸時代中期から明治時代にかけて名を馳せ、一時は「もおか」が「木綿」の代名詞として通用したといわれています。
特に江戸の木綿問屋に大量に売買されていた記録があり、真岡木綿は特に晒し(さらし)の技術に優れ、変色することもなく絹のような肌触りが人気でした。しかし、明治以降、輸入糸の流入により徐々に衰退してしまいます。
真岡木綿は昭和に入ってからはほとんど生産されなくなりましたが、昭和61年に真岡商工会議所が中心となり、「真岡木綿保存振興会」を設立し復興を遂げました。
現在は、真岡木綿会館で県の伝統工芸士4名を含む、13名の機織り技術者が継承しており、綿の栽培から、糸紡ぎ、糸染めから機織りまでをすべて手作業で行っています。
真岡木綿は真岡の市章、市の花、コットベリーなどのキャラクター、市庁舎やmonacaの建物のデザインなどのモチーフとしても、広く市民に親しまれています。

綿の種まき

綿の収穫

染め前の木綿糸

織姫(おりこ)による機織り
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会 文化課 文化振興係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎4階
電話番号:0285-83-7732
ファックス番号:0285-83-4070
お問い合わせはこちら









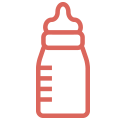
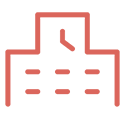
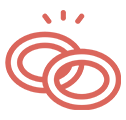

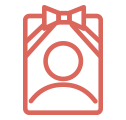
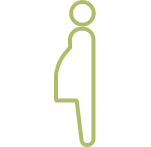



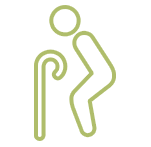







更新日:2025年03月18日