大日堂獅子舞

獅子舞の様子(四方固め)

獅子舞の様子(入羽と四方固めの間)

獅子舞の様子(入羽と四方固めの間)
| 名称 | 大日堂獅子舞 |
| 読み方 | だいにちどうししまい |
| 指定区分 | 栃木県指定無形民俗文化財 |
| 指定年月日 | 昭和29年9月7日 |
| 上演場所 | 大日堂(真岡市中萩1丁目5番地2) |
| 上演日 | 大祭(8月第1土曜日) |
| 保存団体 | 大日堂獅子舞保存会 |
| 概要 | 大日堂は、1658(万治元年)に宝性院胎蔵寺の知善和尚が創立しました。このときから地元民に獅子舞が伝承されるようになり、現代まで大日堂に毎年奉納されています。獅子舞は悪疫、災難除けの舞で、毎年4月の大日堂創立記念日、7月の青谷箸(あおやばし)、8月の大祭とお施餓鬼などで舞われます。大日堂獅子舞は、大獅子、中獅子、女獅子からなる一人立ち三匹の風流獅子舞です。女獅子はお歯黒で牙がないのが特徴です。 |
| 番付及び内容 |
本庭
1.街道下り 笛の音に合わせて、「こうがけ」(麻の紺地)を下ろさずに進んできます。
2.入羽(始めの舞) 「こうがけ」を被って舞い始めます。
3.四方固め 大獅子が太刀で四方を祓い清めます。
4.歌の区切り(舞の切り) 舞の後、座って少し休みます。
5.歌より始める 座っていた獅子が立ち上がって舞い始めます。
6.女獅子隠し 大獅子と中獅子の雄獅子たちが、女獅子を奪い合って激しく争います。その後仲直りをして眠ります。
7.獅子起し 笛の音が低い調べから次第に高くなっていくにつれて、獅子が目覚めて舞い始めます。
8.歓喜の舞い 大獅子と中獅子は歓喜して扇と幣束を持ち、交互に扇の舞を舞います。
9.御道下り 最後の舞を舞った後、「こうがけ」を上げてお山に帰っていきます。 |
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会 文化課 文化財係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎4階
電話番号:0285-83-7735
ファックス番号:0285-83-4070
お問い合わせはこちら









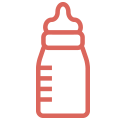
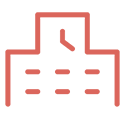
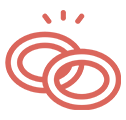

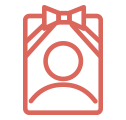
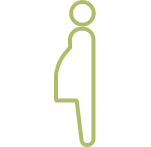



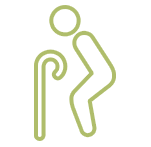







更新日:2025年08月18日