―賀川さんのご活動について教えてください。
真岡市寺内でハーティッチファームを経営しています。夏場は露地、冬場はハウスで、ナスを主作物として栽培しています。ナスは、独特なえぐみや皮の硬さで苦手な方もいらっしゃると思うのですが、そういったデメリットをなるべくなくして、甘みが強くて食べやすいのがハーティッチファームのナスの特徴です。
栽培上のこだわりは土づくり。野菜は、育ちやすい環境をしっかりつくってあげると自然と美味しくなるんです。うちでは、祖父の代から70年以上、野菜栽培用に育てられてきた土に、できるだけ微生物の働きが活性化するよう手を加えています。微生物がよく働くと、土の柔らかさが全然変わってくるんですよ。鉄の棒を刺してみると、耕す前は30センチしか刺さらなかったところが、今は80センチくらい刺さるように。下の方までふかふかの土になっています。ナスの根は60センチほど伸びるので、柔らかい土の中で地中深くまでしっかり根をはり育つことができます。
販売方法にもこだわっています。農協への出荷だけでなく、直接お客様に届けたいと考えて、自社のインターネットでの販売や、民間の産直プラットフォームへの出品をしています。売上は農協が7割で、今年は個人向けの販売が3割まで伸びました。どうやったらダイレクトにお客様に野菜を販売できるか、日々挑戦しています。
その中で生まれたものの一つが「ごほう美ナス」。ナスを買うとき、ほとんどの方はなるべく安いものを買いたいと思っているでしょう。そのような消費材としてのナスではなく、自分のため、大切な人のためにちょっとしたご褒美になるような、ここでしか買えない嗜好材としての美味しいナスを作ろうと考え、形にしました。ごほう美ナスは、一般社団法人日本野菜ソムリエ協会が主催する野菜ソムリエサミットで金賞も受賞しています。
その他にも、珍しいところでは国産胡麻も栽培しています。国内で消費されている胡麻はほとんどが海外産で、国産胡麻の国内流通量は0.1%以下。作業工程が細かく、機械化が難しいため、人手が必要になります。そこを、福祉施設の方に手伝っていただいたり、グリーンツーリズムの体験としてさまざまな方に農業に関わっていただいたりしながら、みんなで胡麻を栽培しています。
胡麻は売上というより、コミュニティづくりのツールとして考えています。長閑な農村風景の中でみんなでワイワイ手を動かして汗をかく。普段農業に関係ない人にも農業に触れてもらう機会になればと思っています。胡麻栽培のコミュニティ「胡(ご)みゅにてぃ~」には、昨年のべ100人以上が参加してくれました。
ー作物をつくるだけでなく、コミュニティ活動も行っているのですね。
さまざまな方に、農業に関わる機会を提供したいと思っています。私は農家で育っているから農業が身近でしたが、一般の人と農業の間には見えない壁があると感じていて。それを取り払って、農業のよさ、大変さなどをもっと身近に感じてもらいたい。農業をもっと近づきやすい職業にしたいと考えています。
胡みゅにてぃ~の他にも、「ナス苗の里親プログラム」も実施しています。里親さまのご自宅の室内で1ヶ月間育ててもらったナスの苗を、ハーティッチファームに返送していただいて畑に移植し大きく育て、収穫したナスを他の野菜とともにお届けするサービスです。食育にもなりますし、家庭菜園などのスペースがないお宅でも気軽に農業体験することができます。
農業は、新規就農する方も法人化する方もいらっしゃいますが、この辺りだと基本的にはほとんど世襲なんですよ。もっと個人レベルでもいろいろな人が挑戦できる業界にしなければ、これから先農業は廃れてしまうと思うのです。
さまざまな体験を通して農業を身近にするとともに、もっと稼げるようにして、就職の選択肢の一つとして認知されるようにしたい。一般の人にとって敷居の低い、入りやすい業界にしていきたいと考えています。














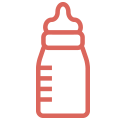
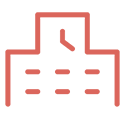
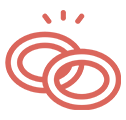

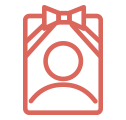
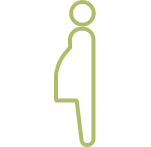



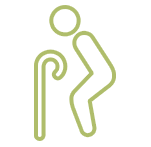







更新日:2025年06月12日