-ありがとうございます。今後やりたいことを教えてください。
以前のそらまめ食堂があった場所に、新しく障害者の就労支援などを行っている手仕事工房そらが飲食店をオープンさせました。その際、以前うちが商売をしていた場所だから、「みどりや」の屋号を使わせてほしいと相談してくれたのです。悩みましたが、ありがたい話だから使っていただくことにしました。
私はずっと、公的な施設に福祉の店をと活動してきました。でも、最近になって、実は母みどりが、あの時代にそれを実現していたことに気が付いたのです。母は夫を亡くして、地域の未亡人の会に所属していました。桜の時期は行屋川に売店を出して、売上を会の活動費にしていました。市役所の軒先に売店を構えていたこともあったんですよ。あの頃はわからなかったけれど、あれこそ福祉、さまざまな立場の人を支える支援でした。母は公的な場所に福祉の店を出した先駆けだったのです。
そんな母の名前をとった店は、煎餅屋と団子屋だった当時の名残を残してもらい、新しく「お餅 和カフェ みどりや」として営業しています。豊富な経験を持つ和食の料理人さんが、障害を持つ人たちのためになればと腕を奮ってくれています。大家として余計なことは言わないように気をつけながら、応援していきたいと思っています。
-渡辺さんから見た真岡はどんなまちですか?どんなまちになっていってほしいですか?
生まれ育って骨を埋めるまちですから、なんて言ったって良いまちにしたいですよねえ。
これからはお年寄りを大切に…と言いたいところだけど、そうじゃないんだよね。若い人たちのアイデアや生き方を尊重できるまち、若者の考えが政策まで届いて、イキイキ頑張れるまちにしてほしいと思います。
女性の社会参加が促されて、障害者が生きやすいまちには、私が言わなくたって、もうなっている。社会が変わってきているのを感じています。男でも女でも障害があってもなくても、人権が守られる状態であるといいですね。
-どうなると、人権が守られている状態になったと言えるでしょうか。
何をやったって「おかしい」と言われないことかな。人はみんな違うから、自分の視点から見たらおかしいかもしれないけれど、他の人が見たら「あら、素敵」となるかもしれない。
私は女が働いて変だよと言われたけれど、食べていくにはお店を頑張らなきゃいけないし、お父ちゃんを幸せにするために一生懸命働くし。私は今もふざけて夫を「この人、私の女房です」なんて言うんだけど、夫は掃除も洗濯も大好き。一方で私は掃除も洗濯もできない、ご飯炊きもできない。うちは飲食店だから、ご飯を作るのはお父ちゃんという係長がいます。レジにお金を入れるのが私の役目。男だから、女だからではなく、そういう風な役割なんです。
目が見えない次女は電車で間違えて人の膝に座ってしまったり、田んぼに落っこちて助けてもらったり、人様にたくさん迷惑もかけたけれど、そのおかげでたくさんの温かい心に触れることができたし、私は良い人生を与えてもらった。障害を持つ人が、人に何かをする側になることは、何もおかしくない。
「おかしい」と思うことも、裏を返すとおかしくない。障害も性別もみんな人それぞれだから、その人その人の多様性が認められる地域社会になると良いなと思います。















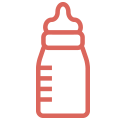
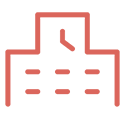
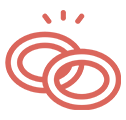

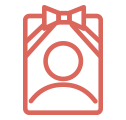
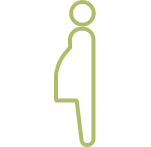



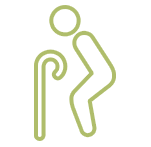







更新日:2025年07月15日