まちつくインタビューvol.13長野大輔さん
「楽しい」のコラボがまちをつくる。協働の実現を目指して。
真岡市の市民活動推進センター「コラボーレもおか」事務局長を務める長野大輔さん。やりたいことのある人が活動しやすくなるよう、アシストする仕事にやりがいを感じているといいます。地域を支える市民活動から、どんなまちづくりを目指すのか。お話を伺いました。

長野 大輔(ながの だいすけ)
栃木県市貝町出身。作新学院高等部卒業後、宇都宮大学で森林科学を学び、環境コンサルティング企業に入社。その後退職し、宇都宮大学大学院に進学。在学中に真岡市の市民活動推進センター「コラボーレもおか」のアルバイトスタッフとして入職。現在は同センター事務局長。日本野鳥の会栃木県支部会員。真岡まちづくりプロジェクトにも携わる。
やりたいことのある人をアシスト
―長野さんのご活動について教えてください。
長野:真岡市のNPO法人ま・わ・たの事務局で働いています。ま・わ・たの活動は大きく3つ。市から受託している市民活動推進センター「コラボーレもおか」の運営、フードバンク、福祉作業所です。
私はその中で、市民活動やボランティアをさまざまな面からアシストする、コラボーレもおかの事務局長を務めています。市民活動やボランティアをしたい人と受け入れたい人、必要な情報や物事をつなげるボランティアコーディネーターという役割ですね。
例えば、「フリースクールをやりたい」という方がいらっしゃったら、事業の相談にのったり、知見のある方々のネットワークを紹介したりします。コラボーレにいらっしゃる方の相談内容は、人を紹介してほしいというものからNPOの設立方法を教えてほしいというものまでさまざま。伴走して支援することもありますし、スキルアップの講座を開くことも。補助金や助成金の情報、寄付の募り方のノウハウなども発信しています。
―そもそも、ボランティアや市民活動とはどんな活動を指すのでしょうか?
ボランティア活動とは自発性、無償性、社会性がある活動のことと定義しています。自発性とは、誰かに強制されるのではなく、自分から進んで物事を行おうとすること。社会性とは、社会全体の利益となること。無償性は、金銭的な見返りを求めないことです。ただ、無償性といっても、活動の際の実費をいただくことはあります。このあたりは誤解されやすい部分ですね。あとは、誰もやっていないことをやるという意味で先駆性が定義に加えられることもあります。
市民活動は社会課題解決のために市井の人々が行う活動のこと。ボランティアも市民活動の一つです。ただ、市民活動の定義は広く、有償で行う活動も含まれます。たとえば営利目的の組織である株式会社のCSR活動などですね。
―なるほど!長野さんはどんなところにやりがいを感じますか。
コラボーレを訪れた方のやりたかった活動が活性化して、花開くのを見るのが喜びですね。自分が中核となって何かを行うよりも、外側で支えることにやりがいを感じます。誰かのアシストができたときが嬉しいです。
コロナ前にはボランティアをしたい方と受け入れ団体とをつなげるイベントを開いていたのですが、そこで良いつながりがつくれたときなどは達成感がありました。今年はボランティアに関心がある高校生と、自治会とをつなげる企画を予定しています。

一度は分からなくなったボランティアのこと、コラボーレで良さを実感
―もともと、コーディネーターの仕事をされたいと考えていらっしゃったのですか?
長野:いえ、全然違う仕事をしていました。小学校のとき鳥に興味を持って、大学で鳥を中心に生態系について学んだんです。その後、環境系NPOでの調査や活動を経て、道路や大規模施設の建設の際、生態系への影響を調べる環境コンサルタントの職に就きました。今も鳥を見るのが好きなので、自然環境保全の活動もしています。
―鳥がお好きなんですね!好きになったきっかけは?
通っていた小学校が、野鳥に親しむことを目的にした「愛鳥モデル校」に指定されていたんです。年に何度も鳥の観察会をしたり、コンクールで活動発表したりしているうちに好きになりました。単純に見ていてかわいいですし、そこにしか生息していない珍しい鳥に出会えるとテンションが上がります。
―研究してお仕事にまでされるのはすごいですね。環境コンサルタントからどのようにして今のお仕事へ?
宇都宮市で環境コンサルタントとして3年ほど働いたのですが、だんだん違和感を覚えるようになりました。私たちは生き物のために調査するけれど、結局は工事をするんですよね。必要な道路や建物をつくる工事はもちろん悪いことではないものの、生き物の生息場所はほぼなくなってしまう場合が多いのです。工事を実施するための調査をしてお金をもらうことに疲れてしまいました。
一度研究の世界に戻ろうと考え、宇都宮大学の大学院に進みました。生活のために鳥の調査のアルバイトをしていましたが、冬になるとほぼ案件がなくなってしまうんです。どうしようかと思っていた時、コラボーレもおかの求人を見つけ、アルバイトに応募しました。
―アルバイトから入ったのですね。コラボーレで働こうと思われたのはなぜですか?
ボランティアって何だろうと疑問に思っていたからです。私は学生のころから野鳥の会やNPOなどのボランティア活動を続けていました。しかしそのころ、イベントを手伝わなくてはならなかったり、年々責任が増してきたりと、しんどくなっていたんです。これまでお世話になってきたから恩返しをしなくちゃ、役割をいただたからやらなくちゃという気持ちが強く、ボランティア活動をすること自体が苦しくて。もっとうまくできないのかなと、ヒントを探して応募しました。
コラボーレには、ボランティアについて専門的に勉強して実践してきた専門員の方がいらっしゃいました。そこで学ぶようになって、もやもやが解消できましたね。ボランティアは自発性が大事。若干無理をしなくてはいけないことはあっても、強制されるものではないと改めて思えたのです。責任感や義務感ではなく、まず自分が楽まなきゃダメだよね、と。個人ではなくチームでやることが大切だとも感じました。
それまではボランティアに対してつらい気持ちがあって、やる気が減っていました。でも、学ぶことでボランティアっていいな、面白いなと思えるようになったのです。もっとさまざまなことを学びたいし、自分のように活動している人がボランティアを嫌いにならないようにしたいと考えるようになりました。それでコラボーレで働くことにしたのです。

長野さんが撮影した、調査や市貝町のまちおこしでも馴染み深い鳥「サシバ」。写真を撮るのも好きだそう。
個人が集まり一緒につくる。まちつくで知った協働
―昨年は、真岡まちづくりプロジェクト(以下、まちつく)でも活動されました。実際に参加されてみていかがでしたか。
長野:コロナで活動自粛が続く中で始められていてすごいなと思い、市民と一緒にやるなら、力になれることがあるかもと参加させていただきました。
始まってみて、メンバーの皆さん一人ひとりに地域をよくしたいという想いがあるのがとても印象的でしたね。大人の方は、それぞれ名前や団体は知っていたものの、つながる機会がなくて。実際に話してみるとこんな面白いことを考えているんだと、自分とは違った目線を知れてよかったです。
まちをより良くするという目的は一緒でも、アプローチが違う。そんな人たちが集まって一緒に何かをつくっていくのは、まさにコラボーレのビジョンにもなっている「協働のまちづくり」だと感じました。
協働という言葉はいろいろなところで使われていて、協働を目的にした施策が生まれることがありますが、誰かと一緒に何かをしたらなんでも協働になるわけじゃないんですよね。協働はあくまで結果。一人ひとりが楽しく活動している中で、同じ方向を見ている人が集まって一緒に進み、より大きな成果が出せた、それが協働できたということだと思うのです。
たとえば五行川河川緑地「RIVER+」チームのプロジェクト。みんながやりたいことを自発的に出し合う中で、ピクニックマルシェを開催したり、ドックランを設置したり、いろいろできました。他のチームも面白い結果が出ていて、まちつくはまさに私の思う協働がたくさん生まれていました。

地域課題を自分たちの手で
―ありがとうございます。最後に、今後の展望を教えてください。
今後は、ボランティアや市民活動についてもっと知ってもらえるよう活動したいです。今はまだ、コラボーレのことをちゃんと伝えられていないと感じます。「事務局がやってよ」「手伝って」「お金出して」などと言われることもありますが、何でも屋ではないんです。
ボランティアや市民活動は、あくまで自発性が大前提。ここは、なにか課題意識があって、現状をどうにかしようと行動したい人をお手伝いするための場所です。それぞれできない理由はあるにせよ、課題に対してまず石を投げることはできるはず。一石を投じて課題を共有するだけでも違うと思いますし、そこからネットワークをつなげていくことも可能です。
私は、地域の課題への対応が最もスピーディーにできるのがボランティアや市民活動の良さだと考えています。以前は、地域のつながりと家庭と行政とが暮らしのうえでの課題を解決していました。でも今は、時代の流れの中で地域や家族の機能が弱まり、隙間ができている。それをどう埋めていくかが課題だと思うのです。企業活動ももちろん大事ですが、収益を考えるとすぐ動けないこともあります。それではカバーできないものをフォローしていくボランティアや市民活動は、世間からは見えにくいけれど必要とされているものだと思うのです。
まちつくもその一つ。すでに1年目の成果が出ていて、イベントをやったことでRIVER+を使いたいという市民の方からの問い合わせにもつながりました。そんな風に、自発的に何かをやりたい方が増えるといいなと思います。まちつくのような活動が増えていくことで、「協働によるまちづくり」ができるはず。行政、支援組織、企業、個人がもっとつながってネットワークができれば、なんでもできちゃうんじゃないかと思うんです。人頼みではなく、自分たちで一緒にやっていく、そんな空気のあるまちにしていきたいです。

まちつくインタビューvol.13長野大輔 (PDFファイル: 976.7KB) (PDFファイル: 950.9KB)
取材、文章、写真 : 粟村千愛(真岡市地域おこし協力隊)
この記事に関するお問い合わせ先
総合政策部 プロジェクト推進課 まちづくり推進係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎3階
電話番号:0285-81-6949
ファックス番号:0285-83-5896
お問い合わせはこちら









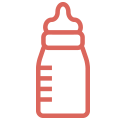
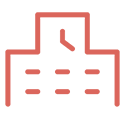
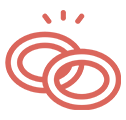

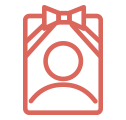
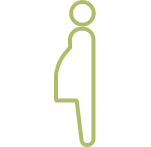



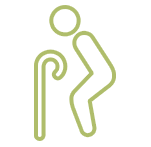







更新日:2023年09月01日