【米農家のみなさまへ】減反政策の廃止とこれからの米づくりについて(主食用米の作付参考値の解説)

減反政策の廃止(生産数量目標の配分の廃止)
平成30(2018)年で、行政による生産数量目標の配分が廃止され、減反政策が終了しました。
農家の方(生産者)は、それぞれの地域の特性等を考えながら、自らの経営判断により、需要に応じた米の生産と販売を行うことになりました。
これからの米づくりの課題
米の消費量の減少
国民1人当たりの1年間の米の消費量については、昭和37(1962)年度の118.3kgをピークに一貫して減少しています。令和3(2021)年度の消費量はピーク時の半分以下の51.5kgでした。
主食用米の需要の減少が見込まれる中、米の消費拡大や需要のある他作物への転換を図り、需要に応じた生産を進めることが必要です。
減反政策の廃止と米づくりに関する質問
減反政策の廃止(生産数量目標の配分廃止)とこれからの米づくりについての質問について、以下のとおりまとめました。
質問1 行政による生産数量目標の配分がなくなるということは、自由に作付け・生産して良いということですか?
生産者個人がより自由に主体的な判断により米の生産量を決められるようになりました。
これからの米づくりは、米の消費量(需要)が人口減少や食の多様化により減少している中、生産者は消費者ニーズにきめ細かく対応した生産を行い、米の需給と価格の安定を図る必要があります。
また、食料自給率・食料自給力の向上等を図る観点から、水田をフル活用し、需要のある麦、大豆、米粉用米、飼料用米等の戦略作物や、野菜、果樹等の高収益作物等への転換を積極的に進めることが重要です。
質問2「生産数量目標」の代わりとなる指標などはありますか?
栃木県農業再生協議会において、需要に応じた米の生産を推進するため、これまでの作付状況等を勘案した「主食用米の作付参考値(面積)」を提示しています。
真岡市農業再生協議会においても、県協議会の作付参考値(面積)を踏まえ、これまでと同じく2月中を目途に、真岡市における「主食用米の作付参考値(面積)」を提示し、農家のみなさまが主体的に米の作付を判断できるよう情報提供を行います。
質問3「主食用米の作付参考値(面積)」とは、どのようなものですか?
国の米政策の見直し(減反政策の廃止)に伴い、平成30(2018)年度から栃木県農業再生協議会が示している、主食用米の生産の目安です。
本協議会でも、県協議会が示した「市町別作付参考値」に基づき、農家のみなさまへ「作付参考値」を通知してきました。
米の作付面積を検討する際には、作付参考値を踏まえながら、集荷業者や農業団体、販売先と十分に相談してください。
質問4 米づくりは今後どうすればいいのですか?
主食用米の需要減少が見込まれる中、需要に応じた米づくりの推進に向けて、生産規模拡大や低コスト技術の導入によるコスト低減への取り組み、米の消費拡大対策、水田フル活用による作付転換(転作)を図ることが重要です。
作付転換については、以下の点を確認してください。
- どの作物に転換するか、早い時期から検討を始めましょう。
- 飼料用米に取り組む場合は、多収品種(夢あおば、月の光)で取り組むことを検討しましょう。
- 水田機能を有する農地においては、連作障害軽減のために水稲と転換作物とのブロックローテーションを行いましょう。
- 転作作物が定着している水田は、畑地化を検討しましょう。
質問5 水田で主食用米以外の作物を作付(転作)した場合の支援は継続しますか?
国による水田フル活用に向けた飼料用米、麦、大豆などの戦略作物への支援や地域の裁量で活用可能な産地交付金による支援(水田活用の直接支払交付金)は継続されます。
また、麦、大豆、そば、なたねの生産及び販売を行う方に対する畑作物の直接支払交付金(ゲタ対策)についても継続されます。
その他、水田の畑地化やその定着を支援する「畑地化促進事業」や、畑作物の低コスト生産等に取り組む生産者を支援する「畑作物産地形成促進事業(旧水田リノベーション事業)」等があります。詳しくは、真岡市農業再生協議会(生産調整推進室)へお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
産業部 生産調整推進室 生産調整係
〒321-4325
真岡市田町1388番地 真岡市農業振興センター内
電話番号:0285-81-3117
ファックス番号:0285-83-8911
お問い合わせはこちら









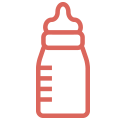
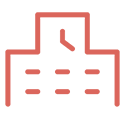
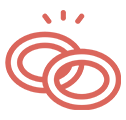

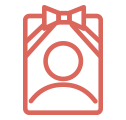
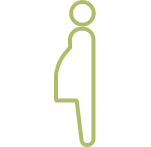



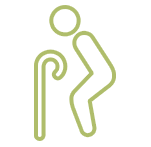







更新日:2024年10月10日