尊徳遺跡コース
桜町在陣中の二宮尊徳の偉業を訪ねましょう。
| 見学場所 | 見学時間 |
|---|---|
|
1.二宮尊徳資料館 |
午前9時~午前9時30分 |
|
2.報徳訓の碑 |
午前9時35分~午前9時45分 |
|
3.史跡桜町陣屋跡 |
午前9時35分~午前10時 |
|
4.新堀川 |
午前10時05分~午前10時15分 |
|
5.八本堰(車で移動) |
午前10時30分~午前10時45分 |
|
6.桜町二宮神社(車で移動) |
午前11時~午前11時10分 |
|
7.二宮金次郎墓域 |
午前11時25分~午前11時35分 |
|
8.蓮城院 |
午前11時40分~午前11時50分 |
1.二宮尊徳資料館

二宮尊徳資料館は、平成12年5月に、桜町二宮神社の境内の一角に開館した。内部は、
- 二宮への道
- 桜町陣屋での実践(仕法)
- 尊徳関連の資料
- 尊徳の足跡
の4つのコースからなっている。二宮尊徳仕法発祥の地として、尊徳の思想や教えを世界に発信する施設である。
2.報徳訓の碑

桜町陣屋南入口の県道に面して建てられている。高さ1メートルの台石の上に鉄柵を廻らせ、高さ240センチメートル、厚さ18センチメートルの粘板岩(仙台石)でできている。 明治18年(1885年)に横山秀一朗(横山周平の孫)が発起人になり、二宮先生の四大門人の一人岡田良一郎(大日本報徳社2代目社長、衆議院議員2期)を始め、静岡・神奈川・栃木の報徳関係者によって建立された。篆額は太政大臣三條實美公、碑文(報徳訓)は金井之恭の書である。
3.史跡桜町陣屋跡(国指定史跡)

桜町陣屋は、小田原藩主大久保家の分家である旗本の宇津家が桜町3ヶ村(横田・物井・東沼)を統治するために元禄12年(1699年)に建てた役所である。現在ある建物は、尊徳が赴任してきた文政6年(1823年)に建てられ、その後数回増改築及び修理が行われたものである。現在の建物の規模は、天保10年(1839年)の屋根葺き替えの記録と一致している。
当時は、敷地内に村役人詰め所、板蔵、材木小屋等、12棟余りあったと伝えられている。また四方に巡らしてあった土塁は、前方(南)と西の一部に旧態をとどめ、その上に立つ桜がはるになると咲いて、盛時を偲ばせている。昭和7年(1932年)に国指定史跡となる。
4.新堀川

尊徳が開発した用水で、陣屋の後方(北)の八本堰より穴川の水を引き入れたもので、そこから発して一直線に南流し、物井の東南部を灌漑して桑ノ川開墾田の東側を経て、茨城県に入って穴川に注ぎ、筑西市奥田で小貝川に合流した。大正6年(1917年)の耕地整理で川の水が変更され、現在はせき止められており、利用されていない。
5.八本堰

八本堰は桜町一帯に灌漑する用水、すなわち新堀川へ水を引き入れるための用水堰である。この堰の築造は直に下流の高田村の耕地に大きく関係をおよぼすものであるから、しばしば水争いが生じた。正徳元年(1711)高田村が代官所に訴え、「堰の築造には杭8本しか立ててはならない」という公儀の裁定がなされ、杭8本、槫8枚で堰を止め、両方の用水路へ適当に配水することとなったことから、「八本堰」という名前が生まれた。現在はコンクリートの水門に改修されている。尊徳の時代にも度々水争いが起きたが、この歴史的事実に基づいて解決したともいわれている。
6.桜町二宮神社

明治三十(1905)年の尊徳を祀って、桜町陣屋内に創建されます。昭和十(1935)年、現在の位置に移されました。
7.金次郎墓域 8.蓮城院

1855(安政二)年に、衰退していた蓮城院を尊徳が現在の場所に移し、再興します。境内の墓地には、遺髪を納めた尊徳の墓のほか、娘の文、領主の宇津釩之助夫妻、同僚の横山周平、弟子の吉良八郎夫妻の墓碑があります。

この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会 文化課 文化財係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎4階
電話番号:0285-83-7735
ファックス番号:0285-83-4070
お問い合わせはこちら









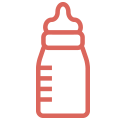
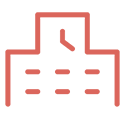
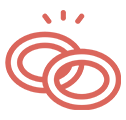

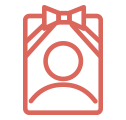
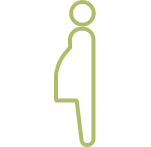



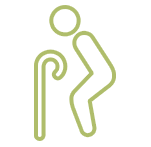







更新日:2023年03月27日